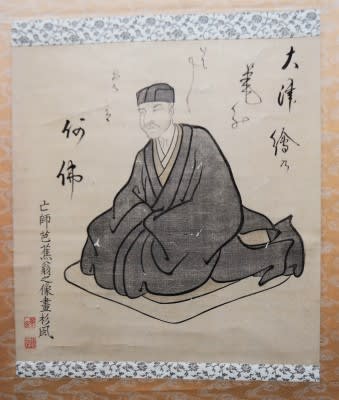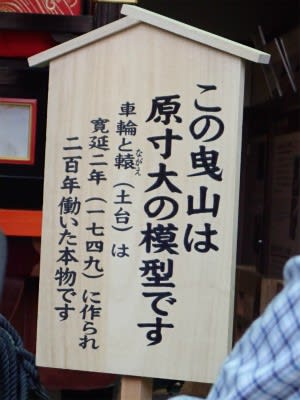わんちゃんが所属するグラウンドゴルフクラブの練習は毎週日曜日の午前中、小学校のグランドでです。
GG仲間のA子さんが「散歩の時にね、東光小の八重桜どうなってるかなぁっと思ってちょっと遠回りして撮ってきたのよ、散り始めのようやけど、まだまだダイジョウブ、わんちゃん今度のバーディ会の後、一緒に見に行かへん?もちろんカメラ必携よ」
![]()
A子さんアリガトーです。
4月28日のこと、練習の後、小学校の正門に回りヤエザクラを見に行きました。
あのヤエザクラででもあります。
東光小学校の正門の前の通りです、まだまだヤエザクラきれいに咲いてます、日曜日なので辺りは静寂に包まれてました。
![]()
![]()
![]()
女の子たちがはしゃいでたあの時を思い出しながら・・・
「ささやきの杜公園」大好きな散策道です。
今頃のモミジも大好きです
![]()
葉がぴちゃッと重ならないで葉と葉の隙間に逆光だと重なった葉っぱが透き通って見えるのです、ソレが良いんですよね。
モミジとは秋に紅葉した状態のことで、イロハモミジと申します。
イロハは葉の裂片を「いろはにほへと」と七つ数えることからついた名前です。
![]()
![]()
竹トンボのように赤いプロペラを広げたモミジの翼果、コレはモミジの種子なんですよ。
風を受けてクルクル回りながら少しでも遠くに飛んでいくような形をしています。
花は春に葉が出るのと同じころ垂れ下がって咲きます。
足元には可愛いお花もいっぱい咲いてます。
ハルジオン (春紫菀)キク科
![]()
北アメリカ原産大正期に渡来。
つぼみの時は茎とともに全体うなだれる。
ブタナ (豚菜)キク科
![]()
ヨーロッパ原産。日本には昭和初期に入ってきたとされ、北海道及び本州の広い範囲に分布。道路脇、空き地、牧場、草原、農耕地の周辺で生育している。
別名:タンポポモドキ
アメリカフウロ (亜米利加風露)フウロソウ科
![]()
北アメリカ原産
冬になると葉っぱが赤く紅葉するんです。こちら
オッタチカタバミ(おっ立ち片喰)カタバミ科
![]()
北アメリカ原産。日本では1965年に京都府で見つかり、現在では各地に分布する.。
カタバミの茎が地表を這うのに対し、地下茎は水平に伸びるものの、そこから地上茎が縦に立つため、この和名がある。
シハイスミレ 紫背菫 スミレ科
![]()
シハイスミレ(紫背菫)は、紫背と書くように葉の裏が紫色を帯びるのが特徴っと教えていただいたことがあったので、まさしく葉の裏が紫色なので、シハイスミレっと。ところが同じような特徴を持っているのに、ヒナスミレやフモトスミレなどがあるという、ちょっと自信のないわんちゃんです。
ヤエムグラ (八重葎)アカネ科
![]()
コレって草ぬきするときなんか軍手にくっついて離れない、そんな時服の胸元にこの花くっつけて「勲章草や」って子供の頃遊んだ記憶がよみがえる。
果実には鉤状の毛が生えているらしい、これも衣服などにくっつく、コレは種子散布に関係するヤエムグラの戦略。
マツバウンラン 松葉海蘭:ゴマノハグサ科
![]()
![]()
海辺に生え蘭に似た花を咲かせる「海蘭(うんらん)」という花の近縁種で、 葉が松葉のように細長いので。
60年程前に初めて京都で確認された北米原産・・・
こうしてグラウンドゴルフの練習後に散歩しながらお花を撮ってて
「そや、あの木も、あの花も撮りたいなぁ、次の練習日(5月2日)にもカメラ持って来ようかな。」
GG仲間のA子さんが「散歩の時にね、東光小の八重桜どうなってるかなぁっと思ってちょっと遠回りして撮ってきたのよ、散り始めのようやけど、まだまだダイジョウブ、わんちゃん今度のバーディ会の後、一緒に見に行かへん?もちろんカメラ必携よ」

A子さんアリガトーです。
4月28日のこと、練習の後、小学校の正門に回りヤエザクラを見に行きました。
あのヤエザクラででもあります。
東光小学校の正門の前の通りです、まだまだヤエザクラきれいに咲いてます、日曜日なので辺りは静寂に包まれてました。



女の子たちがはしゃいでたあの時を思い出しながら・・・
「ささやきの杜公園」大好きな散策道です。
今頃のモミジも大好きです

葉がぴちゃッと重ならないで葉と葉の隙間に逆光だと重なった葉っぱが透き通って見えるのです、ソレが良いんですよね。
モミジとは秋に紅葉した状態のことで、イロハモミジと申します。
イロハは葉の裂片を「いろはにほへと」と七つ数えることからついた名前です。


竹トンボのように赤いプロペラを広げたモミジの翼果、コレはモミジの種子なんですよ。
風を受けてクルクル回りながら少しでも遠くに飛んでいくような形をしています。
花は春に葉が出るのと同じころ垂れ下がって咲きます。
足元には可愛いお花もいっぱい咲いてます。
ハルジオン (春紫菀)キク科

北アメリカ原産大正期に渡来。
つぼみの時は茎とともに全体うなだれる。
ブタナ (豚菜)キク科

ヨーロッパ原産。日本には昭和初期に入ってきたとされ、北海道及び本州の広い範囲に分布。道路脇、空き地、牧場、草原、農耕地の周辺で生育している。
別名:タンポポモドキ
アメリカフウロ (亜米利加風露)フウロソウ科

北アメリカ原産
冬になると葉っぱが赤く紅葉するんです。こちら
オッタチカタバミ(おっ立ち片喰)カタバミ科

北アメリカ原産。日本では1965年に京都府で見つかり、現在では各地に分布する.。
カタバミの茎が地表を這うのに対し、地下茎は水平に伸びるものの、そこから地上茎が縦に立つため、この和名がある。
シハイスミレ 紫背菫 スミレ科

シハイスミレ(紫背菫)は、紫背と書くように葉の裏が紫色を帯びるのが特徴っと教えていただいたことがあったので、まさしく葉の裏が紫色なので、シハイスミレっと。ところが同じような特徴を持っているのに、ヒナスミレやフモトスミレなどがあるという、ちょっと自信のないわんちゃんです。
ヤエムグラ (八重葎)アカネ科

コレって草ぬきするときなんか軍手にくっついて離れない、そんな時服の胸元にこの花くっつけて「勲章草や」って子供の頃遊んだ記憶がよみがえる。
果実には鉤状の毛が生えているらしい、これも衣服などにくっつく、コレは種子散布に関係するヤエムグラの戦略。
マツバウンラン 松葉海蘭:ゴマノハグサ科


海辺に生え蘭に似た花を咲かせる「海蘭(うんらん)」という花の近縁種で、 葉が松葉のように細長いので。
60年程前に初めて京都で確認された北米原産・・・
こうしてグラウンドゴルフの練習後に散歩しながらお花を撮ってて
「そや、あの木も、あの花も撮りたいなぁ、次の練習日(5月2日)にもカメラ持って来ようかな。」